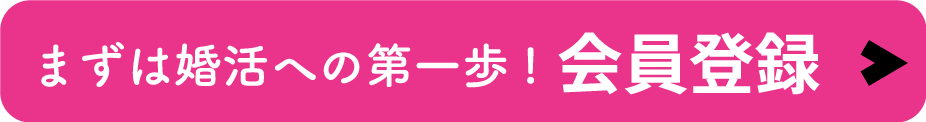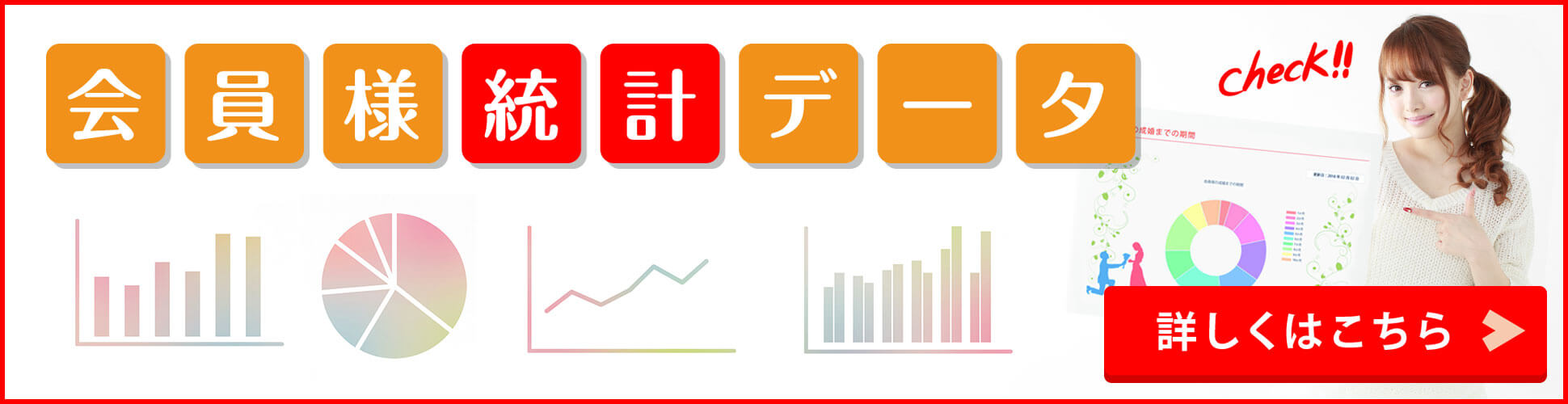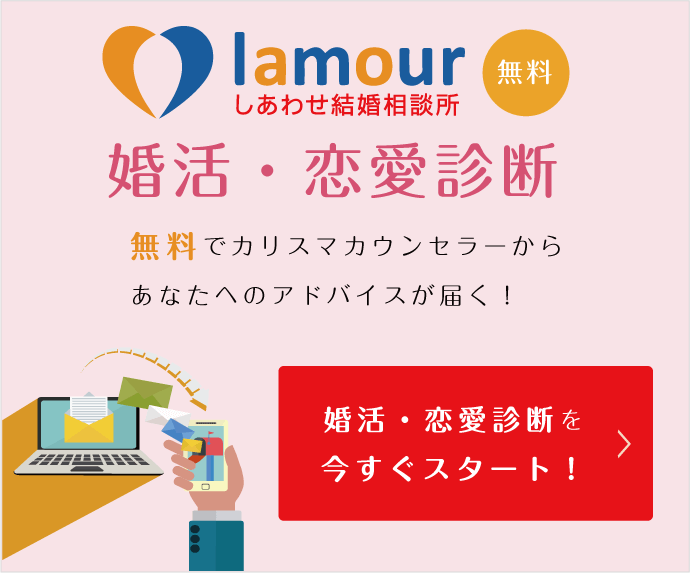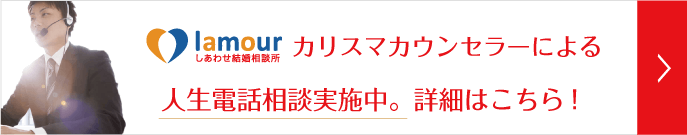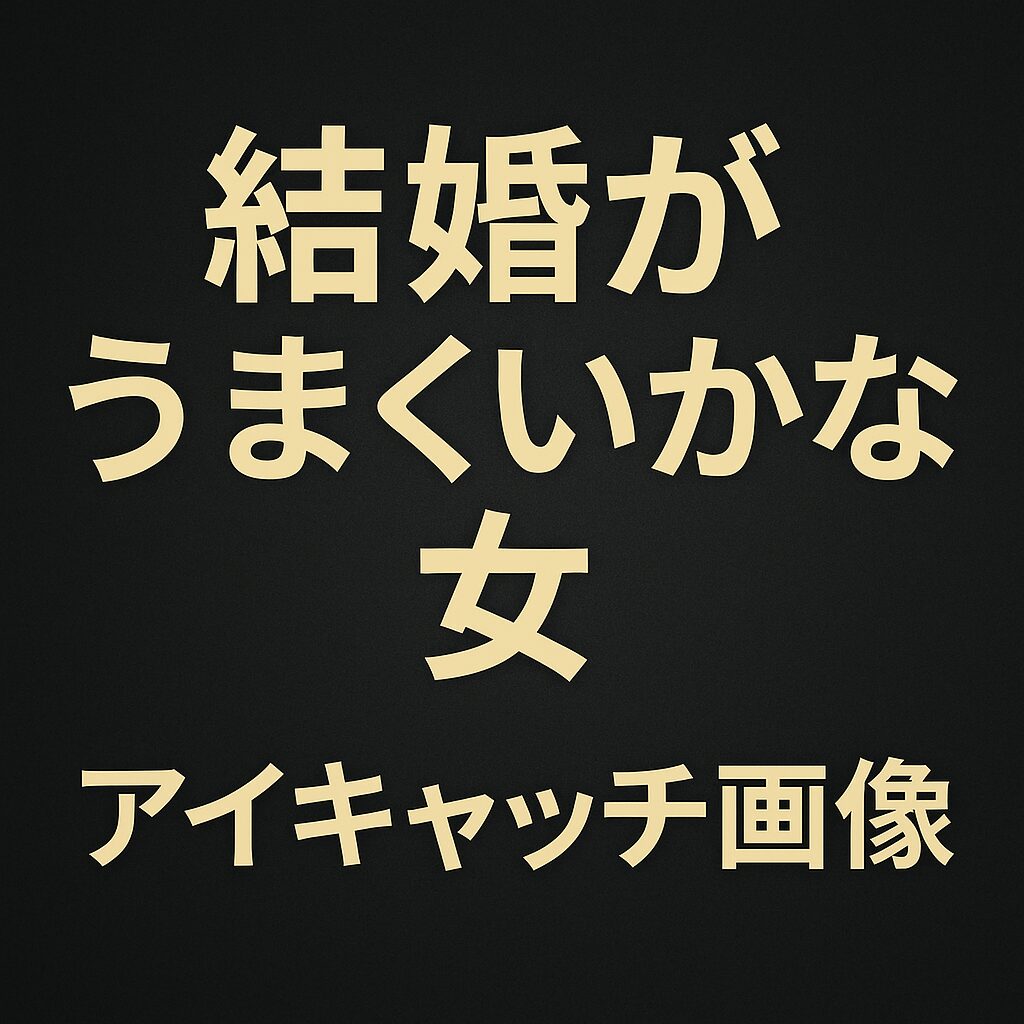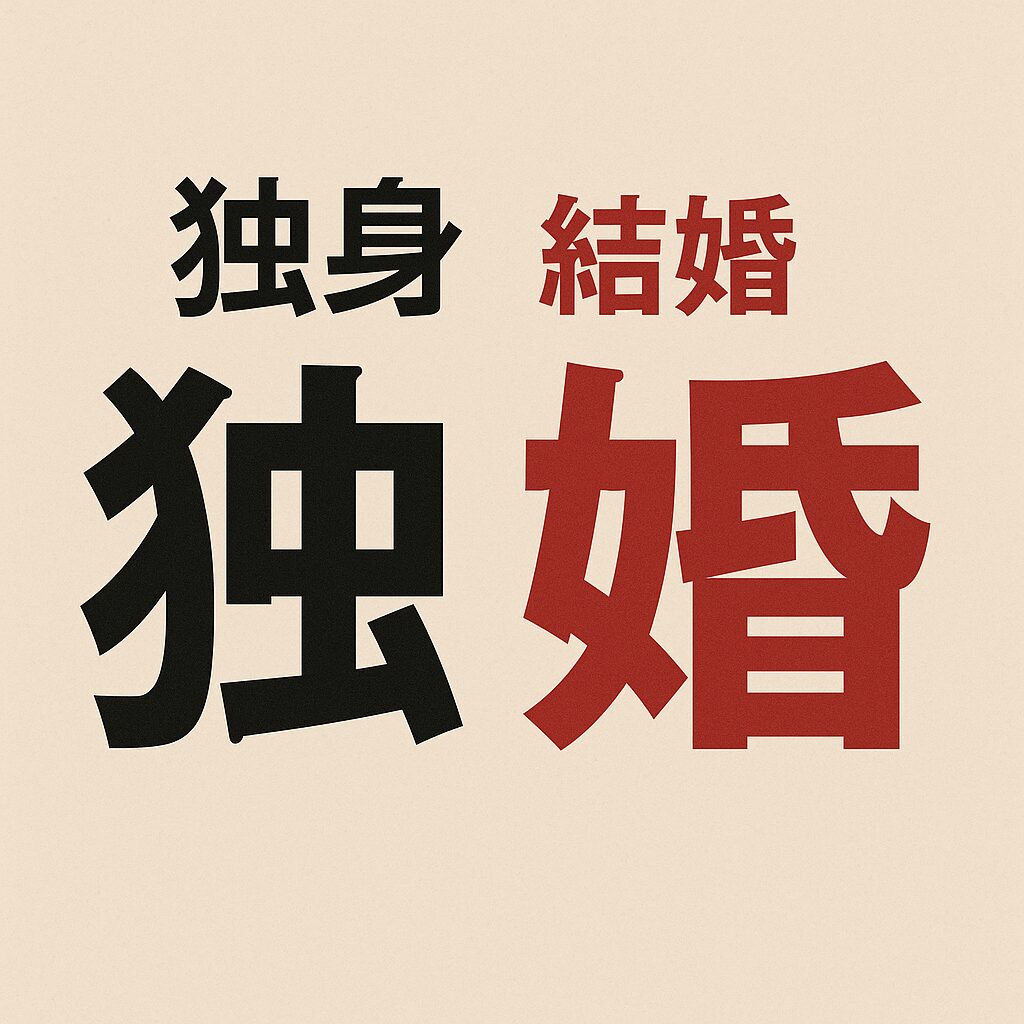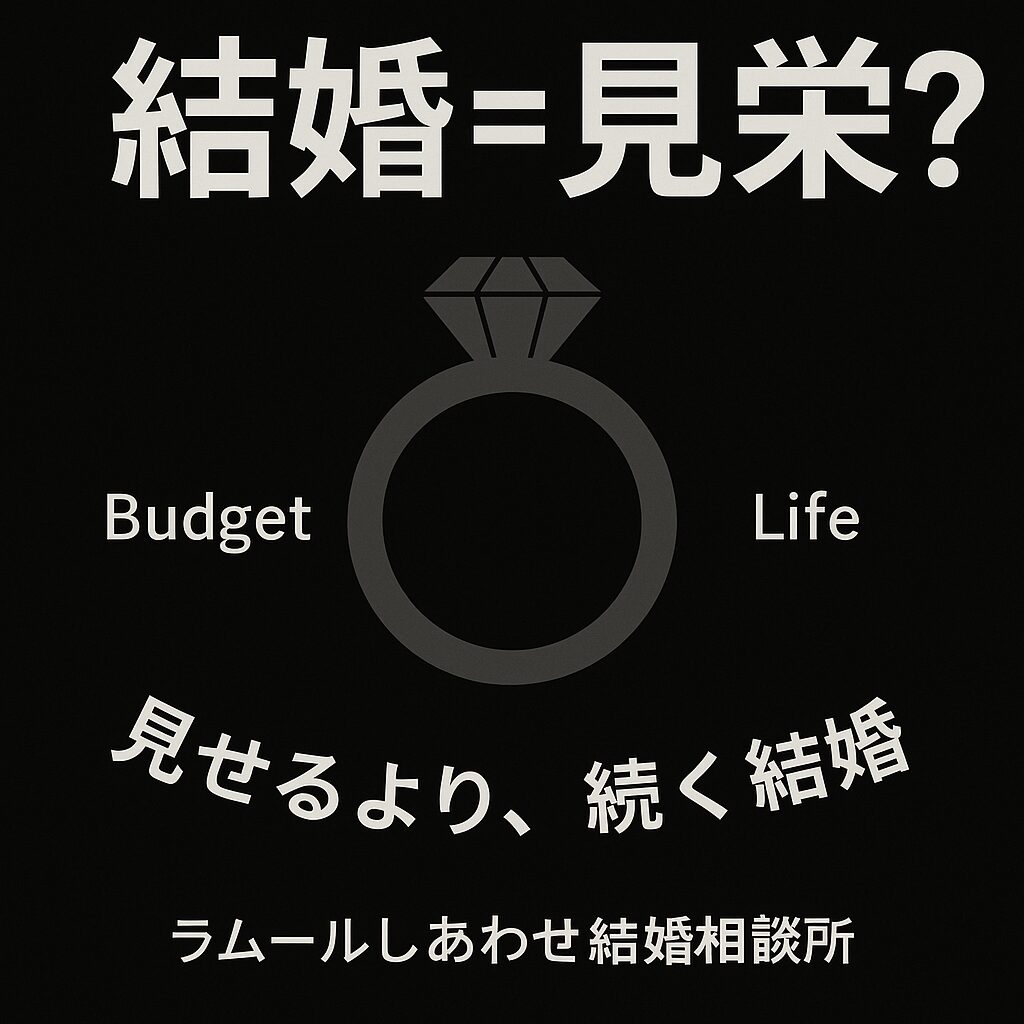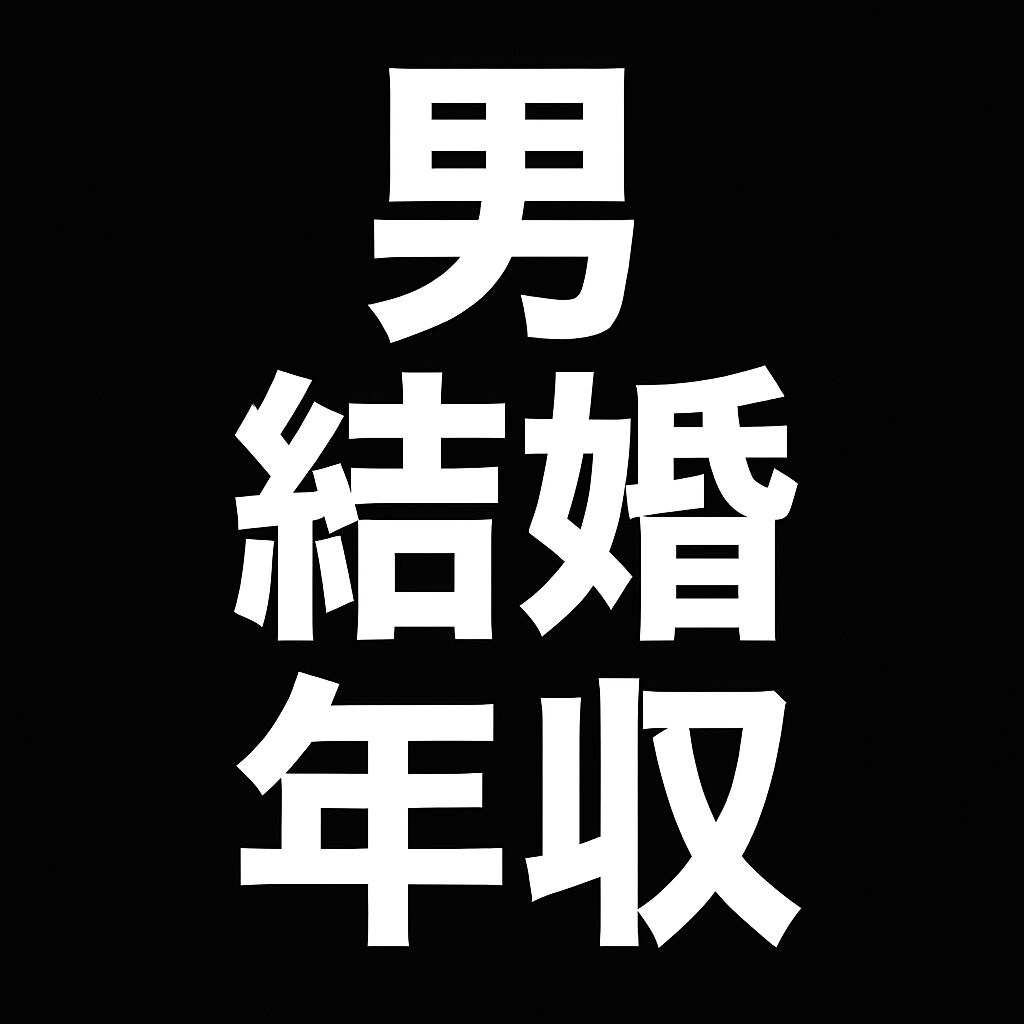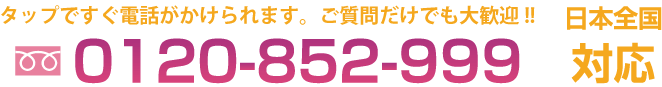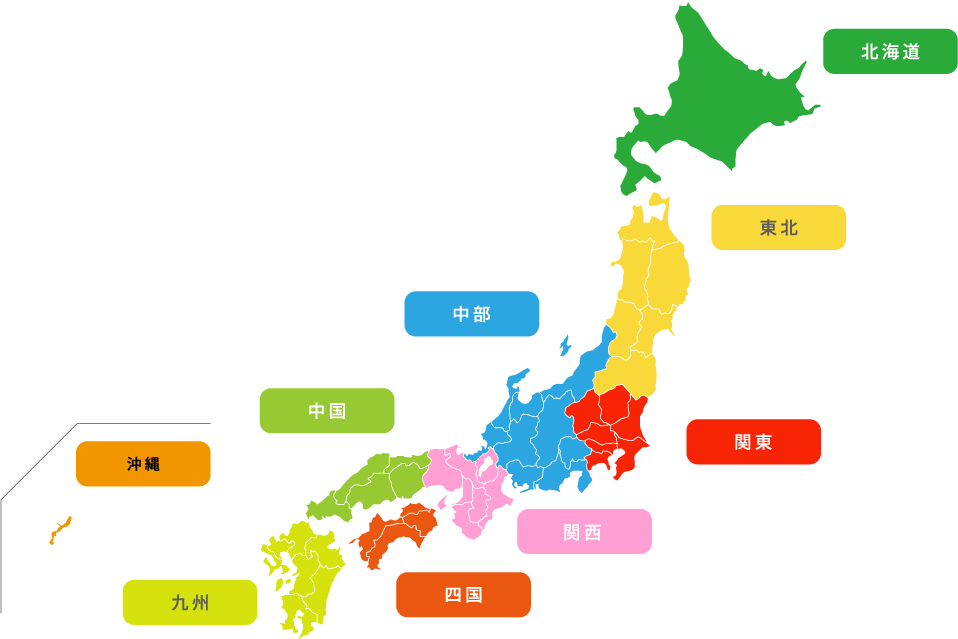当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には、カリスマ仲人にご相談頂いた方が問題解決になる可能性があります。
ご相談は無料ですのでお気軽にラムールしあわせ結婚相談所までお問い合わせ下さい。
婚活ブログ
結婚の謝辞はカジュアルでも感動する!ユニークで短いエピソード

結婚謝辞やウェルカムスピーチは新郎の父親が先に挨拶するケースもありますが、新郎が担う場合が多く両家の代表としての挨拶ですので、新婦はもちろん新婦の親や自分の親、親族や会社の上司、友人など自分達に所縁のあるゲストを前にしてビシッと格好良く決めたいと誰もが思うのではないでしょうか。
これから一家の大黒柱として家族を守るという意思を示すにも、皆が集まる披露宴の席は、最適の場所だと思います。
今回は、結婚式の謝辞にどのようなスタイルがあるのかを書いていきたいと思います。
結婚謝辞の話の流れ
- 結婚謝辞カジュアル
- 新郎謝辞エピソード
- 結婚謝辞や真面目に結婚するなら相談所
- まとめ
結婚謝辞カジュアル

多くのゲストが自分たちの結婚式の為に、都合をつけて集まってくれたことへの感謝の気持ちや今後の抱負などを伝えることが結婚謝辞ですね。
改まった席ですので、難しい言葉を使って大人らしく振る舞いたいと思っている方もいらっしゃると思います。
しかし、人前で話すのが苦手な方やかしこまった雰囲気が苦手という方もいらっしゃるでしょう。そんな方は無理して難しい言葉を使う必要はありません。
新郎新婦の感謝の気持ちを伝えることが一番ですし、難しい言葉を使って紙を見ながら読むよりも、使い慣れた言葉でも紙を見ずに挨拶をする方が気持ちは伝わるのではないでしょうか。
書いてきたものを読む場合でも、ご多用のところ結婚披露宴に出席してくれた方々へのお礼の言葉は、事前に覚えておくと良い印象になるのです。
新郎謝辞感動
新郎謝辞は、結婚披露宴のフィナーレを飾る新郎最大の見せ場でもあります。
「ゲストの方を感動させたい」と思っている方もいるでしょう。しかし新郎ですから、感極まって男泣きしてしまったとしても、堂々とした態度は保ちましょう。
新郎挨拶の最初の部分、ゲストへのお礼から始めます。司会者が「新郎謝辞です」と言っても、会場はまだ賑やかな話し声が聞こえているかもしれません。
そんな中新郎が大声で謝辞を始めるのではなく、会場が賑やかでしたらお辞儀をした後に少し間を置きましょう。
司会者の紹介の後になかなか謝辞が始まらないと、話していたゲストも「あれ?どうしたのだろう?」と思うはずです。会場が静かになったところでスタートさせてみてください。
また、ゆっくりとした話し方は、聞き手に堂々とした印象を与えますので、普段から緊張すると早口になってしまうという方は、ゆっくり大きな声で話すことを心掛けてみると良いですね。
エピソードの部分は感情を込めながら話すと相手の印象に残るでしょう。そして結びの部分へと繋げていきます。
挨拶は内容よりも、新郎の視線や表情・堂々とした態度や感情の込め方に大きく左右されます。抑揚をつけながら聞き取りやすい声で話しましょう。
結婚式謝辞新婦
結婚式での謝辞は新郎の父と新郎が行うことが多いですが、中には新郎と新婦が2人で謝辞を行うカップルもいらっしゃいます。
挨拶のスタイルとしては、新郎・新婦がそれぞれ謝辞を話す場合と、新郎・新婦が交互に1つの謝辞を話す場合があります。
2人で1つの謝辞を交互に話す場合は、始まりと締めの挨拶は新郎にやってもらい、間のエピソードの部分を新婦が挨拶するといった形をとる方もいます。
2人の仲の良い雰囲気が伝わって良いと思いますが、あまり長くならないように気を付ける必要があるでしょう。
新郎謝辞ユニーク
新郎の謝辞は、時間も短めですし、内容も大体決まっていることがほとんどです。「ありきたりの謝辞じゃつまらないから」と、ユニークな謝辞で個性を出し、ゲストの印象に残る謝辞にする方もいらっしゃいます。
当日起こったことや流行っている言葉など盛り込みながら、形式に捉われず、ゲストの笑いを誘うエピソードに仕上げるというのも親しみが湧くので良いかもしれませんね。
新郎父謝辞
新郎謝辞の前にすることが多いのが、新郎父の謝辞です。
内容としては、自己紹介から始め、ゲストへのお礼の言葉、新郎の幼い頃のエピソードや父親から見た息子への想い・新郎新婦へのエールやゲストの方々への2人への力添えのお願いと続けましょう。
そして結びの言葉です。結婚披露宴の不手際を詫びながら、ゲストの幸せを願い、そして改めてゲストへの感謝の言葉で締めるのが一般的な流れになります。
新郎謝辞全文
「謝辞の言葉を考えなきゃ」
「新郎の謝辞って何から話し始めれば良いの?」
とお困りの方もいるのではないでしょうか。難しく考える必要はありません。
謝辞の構成は基本的に3つの構成で成り立っていますので、基本に沿って挨拶文を考えていきましょう。まず初めにゲストへのお礼の言葉です。
都合をつけて自分達の結婚披露宴に出席してくれたこと、また色々な方からの祝辞や祝福を頂いた事への感謝を伝えましょう。次にエピソードです。
無事結婚披露宴の日を迎えられた事への思いや、これからの2人について、なるべく自分達の言葉で伝えられると良いですね。そして結びの言葉です。
これからも自分達2人と変わらずお付き合いいただきたい事と最後にもう一度、今日の感謝の気持ちを伝えます。紙を読んでいた方も、最後の感謝の気持ちはしっかりとゲストの方を向き、お顔を見ながら伝えられると良いでしょう。
新郎謝辞エピソード

謝辞の中で「エピソード」といっても何を話せば良いのか分からないという方もいるのではないでしょうか。
よく2人の出会いのエピソードと勘違いされる方もいますが、新郎謝辞は結婚披露宴のフィナーレを飾るものですので、ここでは出会いのエピソードは話しません。
婚姻されてからの挙式でしたら結婚生活の具体的なエピソードを、婚姻前でしたら結婚式の準備中のエピソードなどを織り交ぜると良いのではないでしょうか。
新郎謝辞短い
「謝辞の言葉を考えて練習してみたら目安の時間よりも大幅に短かった」と悩んでいる方もいるでしょう。
また、披露宴では色々な方々から祝辞を頂戴いたしますし、新郎父からの謝辞もあり、ゲストの気持ちに立つと「新郎の謝辞は短くしたい」と考える方もいらっしゃいます。
謝辞は内容よりも、
「ゆっくりと聞き取りやすく言うこと」
「抑揚をつけて感情を込めること」
「ゲストの方をしっかり見ながら堂々とした態度で話す」
こちらを意識した方がゲストの心に強く刻まれる場合もあります。
新郎謝辞は披露宴の締めとなりますので、ゲストの方も疲れてくる頃でしょうから、短めの挨拶であったとしてもその気遣いがとても嬉しいのではないでしょうか。
新郎謝辞親族のみ
最近は、お互いの親族のみを招いて結婚披露宴をするカップルも増えてきました。親族のみでしたら会社の上司に失礼のないように気負いする必要もありませんので、気持ち的に少し楽になるかもしれません。
ですが、親族のみだからこそ振る舞いには気を付けたいものですね。
新郎謝辞の内容も、親族のみだからとフランクになりすぎるのもあまりオススメではありません。
身内だけの披露宴で、気の置けない方々と楽しい時間を過ごしたからこそ、新郎謝辞では普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを、これまでのエピソードに交えながら伝えましょう。
結婚式新郎ウェルカムスピーチ
ウェルカムスピーチとは、結婚式を執り行った後、披露宴が始まる際に主に新郎からゲストに向けて行うスピーチの事を指します。
内容としては、ゲストへのお礼・無事挙式が行えたこと・披露宴の趣旨・2人の出会いから今の気持ちなどを盛り込みましょう。
披露宴から参加するゲストがいる場合もあるでしょうから、挙式での気持ちや感じたことなどを短めに話すのも良いですね。
披露宴の始まりの挨拶となりますので、あまり長いスピーチですとゲストも辟易してしまうかもしれません。1~2分を目安として内容を考えていきましょう。
まとめ
結婚披露宴のフィナーレを飾るのが結婚謝辞です。
伝えたい感謝の気持ちは沢山あると思いますが、宴の終盤ですのでゲストの方も疲れていることでしょう。
どんなに謝辞の内容が素晴らしく、新郎の立ち居振る舞いも完璧だったとしても、いつまでもダラダラと話していたのでは、ゲストが受ける印象は下がってしまいます。
はっきりと言葉を発し、抑揚をつけながら2分程度を目安にしてくださいね。素敵な結婚披露宴になりますように。
- 公開日:
- 更新日:2024/06/23
この記事は、私が書きました。
結婚の謝辞はカジュアルでも感動する!ユニークで短いエピソード
- 2019/03/27
- 著者: 小渕 栄吾
この記事は、私が書きました。ラムールでは「心理学」「行動心理学」をベースにカウンセリングをおこなっております。年間多くの婚活・恋愛の相談を受ける事で、感じた事や成功方法をお伝え出来ればと思います。「リアル」な記事が多いですので、不快な気持ちになる事もあると思いますが、私は、正直にアドバイスをして来たからこそ年間多くのカップルを作れたのだと思います、少しでも不安に感じる事がありましたらご相談ください。一緒に婚活が出来る事を期待してお待ちしております。
カテゴリー
新着記事5件
人気記事TOP5
入会セミナーご入会・婚活セミナーは各地で行っています。お気軽にご参加ください!
婚活ブログ情報満載のスタッフブログ、好評頂いています!お悩み別の記事なども執筆していますので是非ご愛読ください!
無料メールマガジン登録まずはメルマガから
新規会員さんご入会案内や、イベントのご案内をお送りします。
非会員様でも登録できるので、まずはメルマガからスタートしてもいいですね!